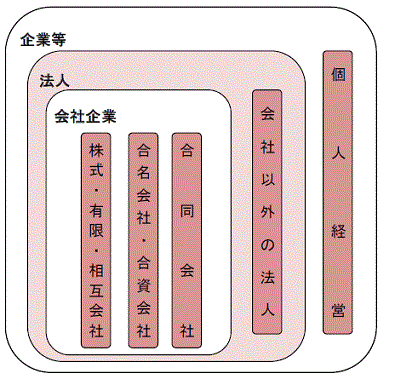インターンのこの人に、「NPO法人って、倒産するんですか?」と聞かれたことから
はじまった、「NPO法人」という不思議な組織のあり方を説明するこの連載。
ちなみに彼(真間ちゃん)が作っているピラフに入れたバターの量がこちら。

痛風一直線!若人たちの健康をお祈りしております。
気を取り直して、前回の復習をはじめましょう。
軽くおさらいしておくと、「NPO法人は、生み出したサービスなどによる
「価値」への対価をもらうことはできるが、その対価を出資した人に再分配する
ことはできない」ということです。
そもそも、「NPO法人」って何?
漢字だらけで意味が分かりづらい、この名前を分解してみましょう。
特定非営利活動+法人と考えます。
ざっくりいうと、「県や一部の市が認めた、「いろんな人のためになる活動」
(=特定非営利活動)」を実施する「法人」という意味です。
特定非営利活動は20項目に分かれていて、
医療や福祉、まちづくりなどに関わる活動が指定されます。
くわしく知りたい方はこちらへ。
「法人」を考えよう。
「団体」、「会社」、「企業」など、「人の集まり」を示す言葉は
他にもいくつかあります。
これらはどのような違いがあるのでしょうか。
まず、「法人」の定義を見てみましょう。
法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。「人」とは、法律的には、権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在をいう。つまり法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在ということになる。
「権利の主体たる資格を認められた存在」、
そしてそれは基本的には「自然人」であるという点がポイントです。
ちょっとむつかしいのですが、踏ん張りどころなのでお付き合いください。
まず、「権利能力」とは「何かすることができる/しなければならない」存在に
なれるということです。
日本国憲法でいえば、11条の基本的人権の尊重や13条の幸福追求権が有名ですね。
ちょっと気にしておくといいのが、「権利能力」とは単に、
何かをすることを認められるだけでなく、自分がしなければならない、
いわゆる「義務」の部分も含んでいる、ということです。
例えば、お給料から引かれる源泉所得税が、医療や介護に使われるように、
自分にとっての「義務」が、他者の「権利」を保障する担保となります。
自分の「権利」を認めるために、他者の「権利」を認める、
すなわち自分の「義務」も引き受けていく存在が「権利主体」です。
さらに、この「権利主体」に慣れるのは、原則「自然人」、
すなわち「生きているそのままの人」であるということです。

生活していると、何かするためにお金が必要だったり、
働いている会社や所属している学校で「あなたはこういう人」と決められたりと、
人以外の大きな「力」とでもいうべき「何か」で自分の存在を
決められることがあります。
でも、逆なんですよね。
現代の法制度の上では、まず「自然に生きているままの人」が
「何かをすることができる/しなければならない」のサイクル、
すなわち権利を持つ主体になれます。
そして、法の上で「この団体だったら、いいよ」と認められた
人(=社団)やお金(=財団)の集合体を「法人」というわけです。
人は、団体に先立つ。
このことは、その場に生きるいわゆる「市民」である「あなた」や「私」の
活動を支援する、NPO法人の事務局を生業としているものとして、
忘れちゃいけないよなぁと日々思っています。
法人と企業と会社
では、この3つの違いを見ていきましょう。
総務省統計局というところが、個人のお店や団体で営んでいる会社など、
すべての「経済を行なう主体」を対象に、その運営の状況を調査する、
「経済センサス」というアンケートがあります。
この調査で、日本で生産された「価値」を産業別に分けた割合や、
そば・うどん屋さんが一番多い県が分かります。
そこで解説されていた、会社と法人と企業の違いが分かりやすかったので、
引用します。
引用:統計局ホームページ/平成26年経済センサス-基礎調査 利用上の注意
意味が狭い順に説明していきましょう。
・会社=営利を創出し、再分配を継続的に行なう目的で作られた人の集まり。
・法人=法人とみなされる条件をクリアした、会社以外の人やお金の集まり。
・企業=法人と認められていなくてもオッケーな、経済活動を行なう主体。
では、「倒産」できるのは?
ようやく本題です。
会社/法人/企業の内、倒産できるのはどれでしょうか。

さきほど、FabLab Kannaiのイスにラスボスっぽく座っていた、中村ryo氏。
前回のおさらいですが、倒産とは、「後払いで買ったものの支払いができなくなる、
など経済の循環を回せなくなる状態」のことです。
とすると、倒産できるために「経済主体」である必要がありますね。
だから、経済をすることを目的に設立された、団体や個人である
会社と企業は倒産できるというわけです。
NPO法人は?
経済活動を行なうことを主目的とする、会社や企業がその活動を
続けられなくなることを「倒産」といいます。
NPO法人は、利益の再分配を行なわない「非営利活動」を行なう団体です。
ですが、その一方で自らが運営する施設を利用された方から
使用料をいただくなどして、 その一方で業務をともにする人への委託費などの
運営費用を捻出しています。
「ある意味経済活動をしていて、またある意味でしていない」
NPO法人は倒産しないのでしょうか?
まず、NPO法人が活動を続けられなくなり、
その存在を消滅させることを「解散」といいます。
前にお話したように、NPO法人は
「特定非営利活動を行なっていくこと」に対して、
「人としての権利能力を認められた」団体です。
すなわち、「活動が行なえなくなる=団体が消滅する」ということです。
会社や企業は、「経済の動きが立ち行かなくなる=主体として消滅する」
ということでしたので、それよりも解散の背景がいろいろあるわけです。
でも、「解散≠倒産」なのでしょうか?
例えば、事務所の家賃が払えなくなって、活動が続けられないから
NPO法人を解散しますということもありそうですよね。
では、解散の理由をくわしく見てみましょう。
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し引用:特定非営利活動促進法
お。六番目の事由に「破産」という言葉がありますね。
破産とは、倒産をちょっと法律用語っぽくした言葉で、
意味はほぼ一緒です。
つまり、「NPOは、破産(≒倒産)を理由として解散することがある」
というのが正解です。
もしNPOが倒産したら?
ここからは、ちょっと補講です。
「無限責任」とは、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して負債総額の全額を支払う責任を負うことを指します。会社がすべての債権を払いきれない場合は、無限責任を負う者は個人の財産をもち出してでも弁済しなければなりません。
(中略)
「有限責任」とは、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として、責任を負うということを指します。つまり、会社がつぶれたときに出資したお金は消えてしまうが、それ以上は責任を負わないということです。
引用:Q523.有限責任と無限責任について教えてください。|ビジネスQ&A|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
株式会社が倒産したときは、出資をした人はその株を買った分の損失だけで済みます。
その一方で、中小企業のオーナー社長は倒産した際に、
金銭を返さないといけない相手から、自分の私財の中から
借金の肩代わりを要求されることがあります。
この状況が「無限責任」というわけですね。
いくつかの事業を展開するために、
出資者を分けて、その責任を分散させることによって、
出資を集めやすくするしくみが株式会社です。
では、NPO法人が破産したとき、理事や社員(=会員さん)は
どのような責任を追うのでしょうか?
まず、そもそもNPO法人は出資によってできた団体ではないため、
上記の有限/無限責任の範囲には入ってきません。
NPO法人が、定款でやると決めた活動をして、
債務(=支払わなければならない金銭)の支払いができなくなったとき、
その債務は団体の債務と考えられます。
よって、会員さんや特定個人が責任を負う、ということは基本ありません。
しかし、団体を管理する立場にある理事さんは、管理者としての義務の
範囲内で負債に対して責任を持ちます。
明らかに返せない借金を、その状況を知りながら
借りた理事は、その借金を償う責任を負います。
つまり、「非営利な活動をしているから、
活動するための資源を他者から得る/その対価を支払うという
経済のサイクルから離れられる」わけではないのです。
社会の中で、必要とされているが再分配のできる営利活動になりづらい
分野をフォローするNPO法人だからこそ、
「信頼」がベースになる団体の形だからこそ、
その経済の循環をちゃんと回していくことが大切だと、
私は考えています。
そして、今社会課題を解決する団体の形はNPO法人以外のものが増えてきています。
例えば、公益社団/財団法人や、LLCと呼ばれるものですね。
また、社会課題を解決するために必ずしも「非営利」にする必要はなくて、
出資者からの賛同が得られれば、株式会社がそうしたソーシャルグッドな事業を
行なうこともできます。
社会に潜む課題を発見し、解決する。
そして、そうした動きをする人たちのつながりを生み出すために、
必要とされる団体とはどういった存在なのか?
環境問題や経済格差など、ちょっとしんどくなっている
今の社会のあり方を変革するための「新しい団体」の形を
探していこうと思います。
参考: